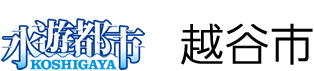更新日:2026年2月20日
ページ番号は111366です。
国登録 有形文化財・建造物 林泉寺 本堂・子安観音堂・鐘楼堂・地蔵堂・表門(赤門)・脇門(黒門)
林泉寺は、市内増林地区の古利根川右岸に位置し、永仁5年(1297年)創建と伝えられる古刹で、市内でも数少ない中世寺院です。
境内には、徳川家康が鷹狩りの際に馬を繋いだと伝えられる越谷市指定文化財「林泉寺駒止めのマキ」があります。
(登録日:令和8年2月10日、国登録有形文化財(建造物)に登録。)
林泉寺本堂
境内東寄りに西に面して建つ本堂は、延宝元年(1673年)頃に建設され、江戸時代に数回改修されています。現在の本堂は昭和45年に大規模改修をしたものですが、天井画や内陣、須弥壇(しゅみだん)などは文政8年(1825年)改修時の姿を残しています。

林泉寺子安観音堂
本堂西方に南に面して建つ子安観音堂は、宝暦12年(1762年)に建設され、全体に建設当初の形式を良く残しています。内部には、厨子に納めた子安観音立像を安置しています。

林泉寺鐘楼堂
本堂の南西に位置する鐘楼堂は、延享5年(1748年)に建設され、組物は絵様肘木(えようひじき)に三斗組を重ねた特徴的な形式となっています。

林泉寺地蔵堂
境内西方に南に面して建つ地蔵堂は、江戸後期に建設され、柱は面取りされた角柱で、組物はなく、桁を柱で直接支えています。内部には、厨子に納めた地蔵菩薩坐像が安置されています。

林泉寺表門(赤門)
本堂の西方に西に面して建つ表門は、宝暦6年(1756年)に建設され、全体が朱塗りされていることから、地元から赤門と呼び親しまれています。棟通りは「扇に日の丸」の浮彫をあしらった蟇股(かえるまた)や、吹寄菱格子(ふきよせひしごうし)で飾っています。

林泉寺脇門(黒門)
赤門の南方に西に面して建つ脇門は、江戸末期に建設され、地元から黒門と呼び親しまれています。正面に冠木(かぶき)風の梁を用いた薬医門形式で、肘木や組物を用いない簡素なつくりの門です。

所在地
越谷市増林3818
このページに関するお問い合わせ
教育総務部 生涯学習課(第三庁舎3階)
電話:048-963-9315
ファクス:048-965-5954