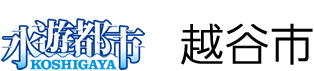ページ番号は58480です。
越谷の歴史 年表(古代〜近代)
| 6世紀後半 | 見田方(大成町)に古墳時代後期の集落がつくられ、人々の生活が営まれるようになった | |
|---|---|---|
| 645 | 大化元 | 大化の改新が始まり、天皇を中心とした律令制による統一国家が樹立されていく |
| 750 | 天平勝宝2 | 大相模不動坊(相模町大聖寺)が創建されたと伝える |
| 771 | 宝亀2 | 武蔵国は東山道より東海道に編入される。以来奥州海道、甲州海道など海道と称された |
| 860 | 貞観2 | 野島に天台宗慈福寺(現在の曹洞宗浄山寺)が創建されたと伝える |
| 939 | 天慶2 | 平将門、王城を建設、新皇と称した |
| 1034 | 長元7 | 大沢(現在の北越谷)の浅間社が勧請されたと伝える |
| 1040〜 | 長久・ 寛徳年間 |
野与党の一族古志賀谷二郎為基や大相模二郎能高が越谷に定住。 野与党の氏神久伊豆宮を祀ったと伝える |
| 1180 | 治承4 | 源頼朝、武蔵国に入り平氏を攻める |
| 1184 | 寿永3 | 源頼朝、大河土御厨を豊受大神宮(伊勢神宮の外宮)に寄進する |
| 1194 | 建久5 | 大河土御厨(越谷の一部を含む八条領など)と越ヶ谷久伊豆宮神人との争いが起きる |
| 1249 | 建長元 | 越谷最大最古の板碑が建立される(現在の御殿町) |
| 1326 | 嘉暦元 | 金沢称名寺文書新方検見帳に恩間の地名が載せられている |
| 1333 | 元弘3 | 鎌倉北条氏滅亡 |
| 1345 | 貞和元 | 足利尊氏、大泊安国寺に利生塔を造塔したと伝える |
| 1461 | 寛正2 | 足利成氏、上杉方と越ヶ谷野に戦い古河に敗走したと伝える |
| 1478 | 文明10 | 越ヶ谷天嶽寺開基と伝える |
| 1562 | 永禄5 | 北条氏康、葛西の本田氏に越谷・舎人(足立区)の両郷を与えるとした文書を発給 |
| 1567 | 永禄10 | 太田氏資、平林寺領馬籠(岩槻)四条(越谷)の領地を安堵する |
| 1569 | 永禄12 | 呑龍上人、平方の林西寺に入り剃髪する |
| 1572 | 元亀3 | 岩槻城代北条氏繁、大相模不動院に掟書を発す |
| 1586 | 天正14 | 太田氏房、大相模不動院に禁制を発す |
| 1590 | 天正18 | 小田原北条氏滅亡。代わって徳川家康関東移封江戸城を本城とするよう命ぜられる |
| 1594 | 文禄3 | 伊奈忠次、利根川を太日川(江戸川筋)に付替え。 これにより鷲宮以南の利根川は廃川となり古利根川と称される |
| 1600 | 慶長5 | 関ヶ原戦の勝利で家康天下に君臨 |
| 1603 | 慶長8 | 家康、江戸に幕府を開く |
| 1604 | 慶長9 | 家康が越ヶ谷御殿を造成する(現在の御殿町) |
| 1617 | 元和3 | 家康廟を日光山に改葬。以来、奥州海道の千住〜宇都宮を日光街道と呼ぶようになる |
| 1625 | 寛永2 | 三野宮・大道・大竹・恩間を岩槻藩領とする |
| 1629 | 寛永6 | 荒川を入間川筋に瀬替。熊谷からの荒川は元荒川と称された |
| 1630 | 寛永7 | 草加宿成立。日光街道はほぼ旧4号国道筋になる |
| 1641 | 寛永18 | 関宿より金杉間の新江戸川開通 |
| 1657 | 明暦3 | 江戸城焼失、越ヶ谷御殿が江戸城二の丸に移される |
| 1660 | 万治3 | 幸手用水路(西用水)が開かれる |
| 1662 | 寛文2 | 見田方・南百・千疋・四条・麦塚・柿ノ木、後に東方忍藩領になる |
| 1680 | 延宝8 | 小菅村から隅田村までの新綾瀬川開通。綾瀬川は排水専用河川となる |
| 1695 | 元禄8 | 越ヶ谷地域などの幕府領総検地 |
| 1696 | 元禄9 | 越ヶ谷宿など日光街道に助郷帳が交付される |
| 1698 | 元禄11 | 砂原・後谷は米倉藩領に、荻島などは旗本知行所に分給される |
| 1704 | 宝永元 | 関東洪水。越谷地域の被害も甚大 |
| 1706 | 宝永3 | 富士山大噴火。越谷地域にも灰が降り不作 |
| 1716 | 享保元 | 鷹場復活。越谷地域も鷹場となる |
| 1742 | 寛保2 | 関東洪水。越谷地域の被害も甚大 |
| 1762 | 宝暦12 | 蒲生一村総検地。名主処罰 |
| 1780 | 安永9 | 大松屋福井家越ヶ谷宿本陣となる |
| 1783 | 天明3 | 浅間山噴火。越谷地域も大凶作。大沢町大火。 |
| 1786 | 天明6 | 関東洪水。越谷地域の被害も甚大 |
| 1792 | 寛政4 | 関東郡代伊奈氏滅亡。家臣会田七左衛門家などの土地は取上げられる |
| 1816 | 文化13 | 大沢町大火。越ヶ谷町山崎篤利・小泉市右衛門・町山善兵衛、平田篤胤の門人となる |
| 1827 | 文政10 | 広域行政による越ヶ谷改革組合などが結成される |
| 1853 | 嘉永6 | アメリカの軍船浦賀来航、通商条約の締結を迫る。越谷地域の農民も御台場構築に協力させられる |
| 1854 | 安政元 | 江戸大地震。越谷地域の被害も甚大 |
| 1864 | 元治元 | 水戸天狗党挙兵。倒伐隊越ヶ谷宿に止宿 |
| 1865 | 慶応元〜 | 長州征伐・御用金を課せられる |
| 1867 | 慶応3 | 徳川幕府大政奉還 |
| 1868 | 慶応4 | (明治元年)薩長を中心とした鎮撫隊越谷に往復。 幕府崩壊。維新政府が樹立される。江戸城が皇居となる |
| 1869 | 明治2 | 越谷地域は大宮県(同年浦和県)と小菅県の管轄となる |
| 1871 | 明治4 | 越谷などは埼玉県となる |
| 1872 | 明治5 | 伝馬制廃止 |
| 1873 | 明治6 | 大沢町に公立の啓明学校が設立される |
| 1874 | 明治7 | 越ヶ谷町大火 |
| 1879 | 明治12 | 郡役所が置かれる 県議会・町村議会が開かれる |
| 1883 | 明治16 | 越谷などは江戸川筋御猟場に指定される |
| 1884 | 明治17 | 越谷などは連合戸長役場に編成される |
| 1889 | 明治22 | 町村制により大相模村など8カ村および越ヶ谷・大沢町組合成立 |
| 1893 | 明治26 | 日光街道、千住〜粕壁間に千住馬車鉄道が開通(後、草加馬車鉄道が大沢まで)。 草加警察越ヶ谷分署が越ヶ谷警察署に昇格 |
| 1894 | 明治27 | 日清戦争が始まる。越谷の出征兵にも戦没者が出る |
| 1899 | 明治32 | 越ヶ谷町大火。東武鉄道千住〜久喜間が開通。越ヶ谷(大沢町)と蒲生(三軒家)に駅が設けられる |
| 1904 | 明治37 | 日露戦争が始まる。越谷の出征兵にも多数の戦没者が出る |
| 1908 | 明治41 | 宮内庁埼玉鴨場が開設される |
| 1910 | 明治43 | 関東洪水。越谷地域の被害も甚大 |
| 1913 | 大正2 | 蒲生の綾瀬川に武陽水陸運輸株式会社が設立される。越ヶ谷町〜大沢町に電灯線が引かれる |
| 1916 | 大正5 | 新方領耕地整理事業完成 |
| 1920 | 大正9 | 東武鉄道越ヶ谷駅が開設され、大沢の旧越ヶ谷駅は武州大沢駅と改称される |
| 1921 | 大正10 | 古利根川大吉の重り土橋が改築され古利根堰と寿橋が建設される |
| 1923 | 大正12 | 関東大震災。越谷の被害も甚大。郡制廃止 |
| 1930 | 昭和5 | 越ヶ谷町立実科高等女学校が県に移管。越ヶ谷高等女学校と称される(現在の越ヶ谷高等学校) |
| 1936 | 昭和11 | 健康保険類似組合「越ヶ谷順正会」が設立 |
| 1941 | 昭和16 | 太平洋戦争が始まる。越谷の出征兵にも多数の戦没者が出る |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 広報シティプロモーション課(本庁舎4階)
電話:048-963-9117
ファクス:048-965-0943