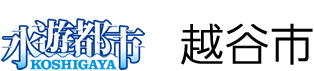更新日:2024年5月31日
ページ番号は8500です。
改正障害者差別解消法がスタートしました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が改正され、令和6年4月1日から施行されました。障がいを理由にした差別をなくし、誰もがいきいきと暮らせる社会をつくっていくため、皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
障がいのある人への差別をなくすために
障がいのある人への差別をなくすための基本的な項目や、国や地方公共団体などの行政機関、会社やお店などの事業者等の対応方法等について定めた「障害者差別解消法」が令和3年に改正され、令和6年4月1日から施行されました。
この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人もすべての人が分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して制定されました。
対象は、障害者基本法に定められた障がいのある人すべてに及び、障害者手帳を持っていない人も含まれます。
障がいを理由とした差別とは?
具体的にどういうことが差別になるのかを判断するための物差しを法律で定めることで、障がいを理由とする差別の解消を推進します。この法律により、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的な配慮を行うこと」が求められています。
〈不当な差別的取扱い〉の禁止
正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、場所や時間帯を制限すること、障がいのない人に付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。
〈合理的な配慮を行うこと〉
障がいのある人から、困っていることを取り除いてほしいなど何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、問題を解決するための合理的な配慮が求められます。困難な状況を解決するために、相手の障がいに合ったやり方や工夫による対応を行わないことは、差別に当たります。
合理的配慮の具体事例等について
合理的配慮の提供について、様々な場面を想定した具体事例が内閣府のホームページ等で紹介されています。合理的配慮の提供は場面や相手によって必要な対応が変わるため正解はなく、以下の事例の対応を強制するものではありません。一つの参考としてご活用ください。
・障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイト)
・内閣府ホームページ(合理的配慮具体例データ集)(外部サイト)
また、合理的配慮の提供を促進する一つのツールとして「コミュニケーション支援ボード」があります。これは、「はい」「いいえ」「ほしい」「わからない」などの意思疎通が指差しで行えるようになっており、会話によるコミュニケーションにバリアのある人への支援を目的として作成された図版となっております。詳細は以下のホームページを参照ください。
改正障害者差別解消法 令和6年4月に施行されたことにより
法律が施行されると、障がいのある人への合理的な配慮について、これまで努力義務とされてきた事業者等も義務化となり、不当な差別的取扱いについては、引き続き禁止となります。なお、この法律では、同一の事業者等によって繰り返し障がいを理由とする差別が行われ、自が主的な改善が期待できない場合などには、国の行政機関がその事業者に対し、報告を求めることや、助言・指導、勧告を行うことができることにしています。
合理的な配慮については、障がいのある人と事業者等が対話を重ね、ともに解決策を探していくことが大切となります。十分な対話を重ね、それでも対応が難しい場合は、障がいのある人に説明して理解を得るよう努めることが求められます。
すべての人がいきいきと暮らしていける社会を目指して
障害者差別解消法は、行政機関や事業者等などを対象とした法律です。
一般の人が個人的な関係で、障がいのある人と接するような場合などについては、対象にしていません。しかし、社会から差別をなくすためには、すべての人が障がいへの理解を深めることが必要です。
障がいを理由とする差別をなくし、誰もがいきいきと暮らしていける社会を目指して、それぞれの立場で考え、行動していきましょう。
相談・連絡先
障がいのある人やその家族等で、差別に関する相談のある人は、下記の問合せ先までご相談またはご連絡をお願いします。
※18歳以上は障害福祉課、18歳未満は子ども福祉課となります。
埼玉県で「埼玉県共生社会づくり条例」が施行されました
埼玉県において障害者権利条約及び障害者差別解消法の趣旨を踏まえた「埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例」(埼玉県共生社会づくり条例)が施行されました。
関連するURL
広報こしがや3月号(7ページ)でも同様のご案内をしています。
内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進) (外部サイト)![]()
障害者差別解消法の詳しい内容は、上記の内閣府ホームページ及び埼玉県ホームページをご覧ください。
埼玉県ホームページ(障害のある人もない人も安心して暮らしていける共生社会に向けて) (外部サイト)![]()
埼玉県共生社会づくり条例の詳しい内容は、上記の埼玉県ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137 ファクス:048-963-9171
子ども家庭部 子ども福祉課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9172 ファクス:048-963-3987