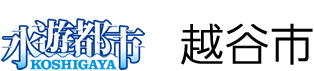更新日:2025年4月7日
ページ番号は9641です。
最適な生育条件を検証するためのコシガヤホシクサの生育試験
越谷市では、「越谷」の名を持つ貴重な植物であるコシガヤホシクサの野生復帰を見据え、種の保全を進めています。市では専門家や関係機関と検討・協議を進めた結果、平成26年(2014年)から、野生復帰に必要となる生育条件のデータ収集などのために、葛西用水路で生育試験を行っています。
これまでの実績
平成26年から平成29年(2014年から2017年)
用水の川底を実験区画として、2月から3月に種をまき、その後4月に用水が入る前には発芽していました。用水が入った後も水中調査を行い、6月頃までは生存を確認できましたが、その後見られなくなっています。毎年、種子の数を増やしたり、水流や水生生物の影響を抑止するネットを外周に設置するなど条件を変えていますが、同様の結果が続きました。
一方、葛西用水路のショウブ田の一部に整備した見本園では、開花し種子を残すことができました。

水中で育っているコシガヤホシクサ
見本園で開花するコシガヤホシクサ
平成30年から令和4年(2018年から2022年)
実験区画を川底より高くして木枠で囲み、より生育しやすい環境を整えました。その結果、用水が入った後も順調に育ち、平成30年の実験から、開花・結実に継続して成功しています。
令和2年8月の実験区画。緑色に見えているのがコシガヤホシクサ。

令和2年9月の実験区画。白い粒のように見えているのが花です。
令和5年(2023年)
コシガヤホシクサの生存個体数が例年より減少し、アメリカザリガニの侵入によりコシガヤホシクサが切られてしまっている可能性が高いことが判明しました。環境の変化にいかに適応するか、新たな課題が見つかりました。
 令和5年試験区
令和5年試験区
 ザリガニの掘った穴が多数見られました
ザリガニの掘った穴が多数見られました
令和6年(2024年)の試験結果
令和5年度の試験で課題となったアメリカザリガニへの対策として、国立科学博物館筑波実験植物園の助言の元、アメリカザリガニの侵入を防ぐ「完全防御区」を導入しました。
四角い木枠の全面をネットで覆い、その内側でコシガヤホシクサの播種を行いました。
完全防御区により、アメリカザリガニや小魚の侵入を防ぐことはできましたが、4月下旬の発芽直後の時期に、数日間にわたる水位の極端な低下があったためか、多くの個体が消失する結果となりました。
実験前の状態(4月)
 試験区全体像
試験区全体像
 完全防御区:下部と上部にもネットを取り付けます
完全防御区:下部と上部にもネットを取り付けます
結実(11月)
11月中旬には、コシガヤホシクサは枯れ、茎の先端部分に種子が作られます。
次回の実験に使うため、可能な限り種子を採取しました。

1年草のため、コシガヤホシクサは枯れています

閉じられた空間内のため雑草の繁茂も見られました
令和7年(2025年)の生育試験
次の2点について条件を変えて試験を行います。
(1)ネットを二重にした完全防御区の増設
(2)葛西用水路の水位安定後の播種の実施(4月下旬又は5月上旬予定)
令和7年度の試験についても、追って成果を掲載します。
播種実験の場所
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9183
ファクス:048-963-9175