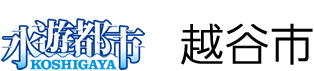更新日:2024年1月18日
ページ番号は7265です。
O157などの腸管出血性大腸菌感染症を予防しましょう
腸管出血性大腸菌感染症とは
腸管出血性大腸菌感染症とは、腸管出血性大腸菌による感染症です。年間を通して発生しますが、湿度や気温が高く細菌が増えやすい、初夏から初秋に多く発生する傾向があります。腸管出血性大腸菌は感染力が強く、水や食物を介して感染し、その後、人から人へも感染します。手洗いを徹底し、食品の取り扱いに注意しましょう。
特徴
大腸菌はほとんどが無害ですが、中には毒素を産生し、下痢などの症状を引き起こすものがあります。これが腸管出血性大腸菌感染症と呼ばれ、代表的なものにO157があります。他にもO26、O111、O128などもあります。
- 感染力が非常に強く、水中や土中では、数週間から数か月生存します。
- 低温に強く、冷蔵庫の中でも生存できます。
- 酸性に強く、口から入った菌の多くは、胃酸に負けず生き残ります。
- 熱に弱く、75℃、1分間の過熱で死滅します。
症状
- 2日~9日(平均3日~5日)の潜伏期間の後、激しい腹痛を伴った下痢(水様)が何度も起こり、血便が出ることもあります。
- 乳幼児や高齢者では、重症化する場合があります。
- 成人などの体力のある方の場合は、感染しても無症状や軽い下痢などで経過し、この病気と気づかない場合があります。
- 症状自体は治まってきても、菌は1~2週間腸内に残り、便とともに排泄されます。
予防対策
- 排便後、乳幼児のおむつ交換後、調理前には、石けんと流水で手をしっかり洗いましょう。
- 調理器具と冷蔵庫は清潔に保ちましょう。
特に、生肉を取り扱ったあとは、まな板・包丁・ふきん等の器具類は、十分洗浄し、熱湯や台所用塩素系漂白剤などで殺菌をしましょう。 - 調理時には十分な加熱(75℃、1分以上)をしましょう。
- 調理したものは、早めに食べましょう。
腹痛、下痢などの初期症状があった場合は医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。
特に乳幼児、高齢者の方など抵抗力の弱い方は、重症化する可能性がありますので、医師の診察を受け、適切な治療を受けてください。
身近に感染者がでた場合は、おう吐物、便の処理の際、マスクや手袋をして処理し、処理後は手洗いを十分にしましょう。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534