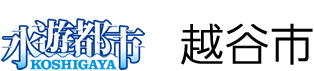更新日:2025年5月16日
ページ番号は84296です。
麻しん(はしか)に注意しましょう
麻しんとは
麻しんは麻しんウイルスによる感染症で、一般的には「はしか」と呼ばれることもあります。
感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染です。ヒトからヒトへ感染しその感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%で発症するといわれています。
平成27(2015)年3月、日本は麻しんの排除状態にあることがWHO(世界保健機関)から認定されました。しかし、海外では麻しんが流行している地域もあり、海外からの輸入例を発端として、平成27年以降も国内での患者報告が確認されていることから、注意が必要です。
海外での流行状況については、下記リンクからも確認できます。
症状
約10日ほどの潜伏期間を経て、発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。熱が一時下がる頃コプリック斑(口の中の粘膜にできる白い斑点)が出現します。その後39度以上の発熱とともに発疹が出現します。
肺炎、中耳炎を合併しやすく、まれに、重い脳炎を発症することもあります。先進国であっても、1,000人に1人の割合で死亡するといわれているため、症状がある場合は、医療機関を受診しましょう。
感染経路
原因となるウイルスは、感染者や患者の咳やくしゃみの飛沫(しぶき)などに含まれています。
(1)飛沫・空気感染:感染した人の咳やくしゃみなどに含まれるウイルスが、鼻や口から侵入することで感染します。
(2)接触感染:ドアノブや手すりなどを介して手に付着したウイルスが、目、口、鼻の粘膜から侵入して感染します。
感染を予防するには
麻しんウイルスは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い・マスクのみでは予防できません。麻しんの予防接種が最も効果的な予防法といえます。定期接種対象者(1歳児、小学校入学前1年間の幼児)、医療・教育関係者、海外渡航を計画している方は、予防接種が済んでいるか確認をしましょう。
ワクチン接種歴は母子手帳等で確認できます。
医療機関を受診する際の注意点
麻しんを疑う症状が現れた場合は、受診する前に医療機関へ連絡し、医療機関の指示に従って受診をしてください。症状がある間は、免疫のない人に感染させてしまうため、移動の際は、可能な限り公共交通機関等の利用を避けるようお願いいたします。
救急の医療機関や電話相談について
受診を迷った場合や夜間・休日の場合は「こどもの救急」などのWebサイトを参照したり、#8000(こども医療相談)にご相談ください。
#7119 (埼玉県救急電話相談)もご利用できます。
(ダイヤル回線・IP電話・PHS・都県境の地域で御利用の場合) 048-824-4199
急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。
音声ガイダンスに応じて、相談したい窓口を選択してください。
ご自身の状態に応じた緊急度判定のアドバイスは子どもの相談又は大人の相談にて行っています。
(1)子どもの相談 (小児救急電話相談) ※対象:中学生まで
(2)大人の相談 (大人の救急電話相談)
(3)医療機関案内(子供・大人に対応しています)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534