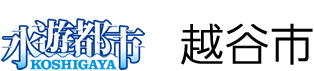更新日:2024年1月18日
ページ番号は74893です。
RSウイルス感染症を予防しましょう
RSウイルス感染症とは
RSウイルス感染症は、RSウイルスによる呼吸器感染症であり、夏から秋にかけて増加する傾向があります。
RSウイルス感染症の流行情報について知り、日頃から予防対策を心がけましょう。
症状
2~7日の潜伏期を経て、鼻汁や咳、38~39度の発熱など風邪様の症状が数日続く感染症です。多くの方は軽症で回復しますが、重症化した場合は、細気管支炎や肺炎などを起こします。
生後6か月以内の新生児・乳児への感染や、低出生体重児、心臓、肺、神経、筋肉などに基礎疾患がある場合や免疫不全がある場合などには重症化の可能性が高まるため注意が必要です。
機嫌がよく、つらそうでなければ、慌てずに様子をみたり、かかりつけ医にご相談ください。
ただし、呼吸が苦しそう、食事や水分摂取ができない時は医療機関への受診をご検討ください。
感染経路
原因となるウイルスは、感染者や患者の咳やくしゃみの飛沫(しぶき)などに含まれています。
(1)飛沫感染:感染した人の咳やくしゃみなどに含まれるウイルスが、鼻や口から侵入することで感染します。
(2)接触感染:ドアノブや手すりなどを介して手に付着したウイルスが、目、口、鼻の粘膜から侵入して感染します。
感染を予防するには
・手洗いをしっかりしましょう
流水、石鹸による手洗いは、手指についたウイルスを除去するために有効です。
・飛沫感染対策としてのマスクを着用しましょう
咳やくしゃみによる飛沫(しぶき)を浴びないようにすれば、感染する機会が減少します。患者さんと接触する際はできるだけ、マスクを着用しましょう。
・子どもが日常的に触れるおもちゃなどの消毒をしましょう
救急の医療機関や電話相談について
受診を迷った場合や夜間・休日の場合は「こどもの救急」などのWebサイトを参照したり、#8000(こども医療相談)にご相談ください。
#7119 (埼玉県救急電話相談)もご利用できます。
(ダイヤル回線・IP電話・PHS・都県境の地域で御利用の場合) 048-824-4199
急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。
音声ガイダンスに応じて、相談したい窓口を選択してください。
ご自身の状態に応じた緊急度判定のアドバイスは子どもの相談又は大人の相談にて行っています。
(1)子どもの相談 (小児救急電話相談) ※対象:中学生まで
(2)大人の相談 (大人の救急電話相談)
(3)医療機関案内(子供・大人に対応しています)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534