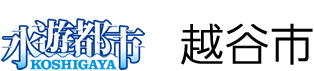更新日:2023年9月1日
ページ番号は8229です。
介護保険要介護・要支援認定申請(新規・区分変更・更新)
要介護(要支援)認定 新規申請
申請が必要なとき
以下に該当する方で、介護保険サービスの利用を希望するとき
- 1号被保険者(65歳以上)で、介護サービスが必要な人(介護が必要になった原因を問いません。)
- 2号被保険者(40歳から64歳まで)の医療保険加入者で、下記16種類の特定疾病により、介護サービスが必要な人(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。)
| 16種類の特定疾病 | |||
|---|---|---|---|
| 筋萎縮性側索硬化症 | 後縦靱帯骨化症 | 骨折を伴う骨粗しょう症 | 多系統萎縮症 |
| 初老期における認知症 | 脊髄小脳変性症 | 脊柱管狭窄症 | 早老症 |
| 糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症 |
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | 脳血管疾患 |
進行性核上性麻痺 |
| 閉塞性動脈硬化症 | 関節リウマチ | 慢性閉塞性肺疾患 | がん末期 |
申請に必要なもの
- 要介護認定・要支援認定申請書(PDF:337KB) (※1)
- 介護保険被保険者証
- 2号被保険者(40歳から64歳まで)の方は、医療保険被保険者証
- 診察券・診療予約票など、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関の所在地・名称がわかるもの(※2)
※1 記入の際は、「要介護認定等申請書 記入例(PDF:391KB)」を参照ください。
※2 認定に際して、医師の意見書が必要になります。介護を必要とする原因疾患などについて意見を書くことができる医師を主治医(かかりつけ医)としてください。また、介護認定に際し、主治医意見書を書いてもらえるかどうか、被保険者ご本人やご家族などから医療機関へ電話等で確認してください。
- 被保険者ご本人以外のご家族や成年後見人等が申請する場合は、上記1から4までの書類のほか、代理で申請するご家族や成年後見人等の本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)も申請時に窓口で提示してください。
郵送による申請について
申請は、郵送で行うこともできます。
郵送の場合は、以下の書類を介護保険課まで郵送してください。
- 要介護認定・要支援認定申請書(PDF:337KB) (※1)(※2)
- 介護保険被保険者証
- 2号被保険者(40歳から64歳まで)の方は、医療保険被保険者証の写し
※1 申請書の記入の際は、「要介護認定等申請書 記入例(PDF:391KB)」を参照ください。
※2 認定に際して、医師の意見書が必要になります。介護を必要とする原因疾患などについて意見を書くことができる医師を主治医(かかりつけ医)として、申請書に記入してください。また、介護認定に際し、主治医意見書を書いてもらえるかどうか、被保険者ご本人やご家族などから医療機関へ電話等で確認してください。
- 被保険者ご本人以外のご家族や成年後見人等が申請する場合、上記1から3までの書類のほか、代理で申請するご家族や成年後見人等の本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写しもあわせて送付してください。
- 申請書を受け付けした後に、申請者へ連絡し、被保険者ご本人の状況把握や認定調査の日程調整などを行います。
電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、下記リンクより電子申請することもできます。
※マイナンバーカードのほか、パソコン・ICカードリーダライタ、マイナポータルアプリ対応のスマートフォン等が必要です。
※申請受付後に、申請者へ連絡し、被保険者ご本人の状況把握や認定調査の日程調整などを行います。
市民税非課税世帯の利用者負担額の軽減について
市民税非課税世帯の方が介護サービスを利用したときの利用者負担額を軽減いたします。
要介護や要支援の認定が出る前に暫定的に介護サービスを利用される場合は、「介護保険負担限度額認定申請書」や「介護保険居宅サービス利用者負担額減額(免除)申請書」を要介護認定・要支援認定申請書と併せて提出してください。
暫定的な利用に関する注意
要介護や要支援の認定が出る前に、仮に定めた介護サービス計画(ケアプラン)に基づき、介護サービスを利用することができます。
ただし、認定結果が非該当となったとき、または暫定的なケアプランに設定した要介護度等よりも低くなったときは、介護サービスに要する費用の全部または一部が自己負担になる場合があります。(区分変更申請や更新申請の場合も、同様です。)
ご注意ください。
要介護(要支援)認定 区分変更申請
申請が必要なとき
要介護(要支援)認定を受けている人で、身体の状況の変化等により認定内容の変更を希望するとき
申請に必要なもの
- 要介護認定・要支援認定区分変更申請書(PDF:292KB) (※1)
- 介護保険被保険者証
- 2号被保険者(40歳から64歳まで)の方は、医療保険被保険者証
- 診察券・診療予約票など、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関の所在地・名称がわかるもの(※2)
※1 申請書の記入の際は、「区分変更申請書 記入例(PDF:342KB)」を参照ください。
※2 認定に際して、医師の意見書が必要になります。介護を必要とする原因疾患などについて意見を書くことができる医師を主治医(かかりつけ医)としてください。また、介護認定に際し、主治医意見書を書いてもらえるかどうか、被保険者ご本人やご家族などから医療機関へ電話等で確認してください。
- 被保険者ご本人以外のご家族や成年後見人等が申請する場合は、上記1から4までの書類のほか、代理で申請するご家族や成年後見人等の本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)も申請時に窓口で提示してください。
郵送による申請について
申請は、郵送で行うこともできます。
郵送の場合は、以下の書類を介護保険課まで郵送してください。
- 要介護認定・要支援認定区分変更申請書(PDF:292KB) (※1)(※2)
- 介護保険被保険者証
- 2号被保険者(40歳から64歳まで)の方は、医療保険被保険者証の写し
※1 申請書の記入の際は、「区分変更申請書 記入例(PDF:342KB)」を参照ください。
※2 認定に際して、医師の意見書が必要になります。介護を必要とする原因疾患などについて意見を書くことができる医師を主治医(かかりつけ医)として、申請書に記入してください。また、介護認定に際し、主治医意見書を書いてもらえるかどうか、被保険者ご本人やご家族などから医療機関へ電話等で確認してください。
- 被保険者ご本人以外のご家族や成年後見人等が申請する場合、上記1から3までの書類のほか、代理で申請するご家族や成年後見人等の本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写しもあわせて送付してください。
- 申請書を受け付けした後に、申請者へ連絡し、被保険者ご本人の状況把握や認定調査の日程調整などを行います。
電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、下記リンクより電子申請することもできます。
※マイナンバーカードのほか、パソコン・ICカードリーダライタ、マイナポータルアプリ対応のスマートフォン等が必要です。
※申請受付後に、申請者へ連絡し、被保険者ご本人の状況把握や認定調査の日程調整などを行います。
要介護(要支援)認定 更新申請
申請が必要なとき
要介護(要支援)認定を受けている人で、引き続き介護サービスの利用を希望するとき
※ 有効期間が満了する前に更新手続きが必要です。
※ 更新申請は、原則、有効期間の満了日の60日前から受け付けします。(例:有効期間が7月31日までの場合、更新申請の受付は6月1日からとなります。その日が閉庁日の場合は次の開庁日からとなります。)
申請に必要なもの
- 要介護更新認定・要支援更新認定申請書(PDF:337KB) (※1)
- 介護保険被保険者証
- 2号被保険者(40歳から64歳まで)の方は、医療保険被保険者証
- 診察券・診療予約票など、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関の所在地・名称がわかるもの(※2)
※1 申請書の記入の際は、「要介護認定等申請書 記入例(PDF:391KB)」を参照ください。
※2 認定に際して、医師の意見書が必要になります。介護を必要とする原因疾患などについて意見を書くことができる医師を主治医(かかりつけ医)としてください。また、介護認定に際し、主治医意見書を書いてもらえるかどうか、被保険者ご本人やご家族などから医療機関へ電話等で確認してください。
- 被保険者ご本人以外のご家族や成年後見人等が申請する場合は、上記1から4までの書類のほか、代理で申請するご家族や成年後見人等の本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)を申請時に窓口で確認することがあります。
郵送による申請について
申請は、郵送で行うこともできます。
郵送の場合は、以下の書類を介護保険課まで郵送してください。
- 要介護更新認定・要支援更新認定申請書(PDF:337KB) (※1)(※2)
- 介護保険被保険者証
- 2号被保険者(40歳から64歳まで)の方は、医療保険被保険者証の写し
※1 申請書の記入の際は、「要介護認定等申請書 記入例(PDF:391KB)」を参照ください。
※2 認定に際して、医師の意見書が必要になります。介護を必要とする原因疾患などについて意見を書くことができる医師を主治医(かかりつけ医)として、申請書に記入してください。また、介護認定に際し、主治医意見書を書いてもらえるかどうか、被保険者ご本人やご家族などから医療機関へ電話等で確認してください。
- 被保険者ご本人以外のご家族や成年後見人等が申請する場合、上記1から3までの書類のほか、代理で申請するご家族や成年後見人等の本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写しもあわせて送付してください。
- 更新申請については、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに認定調査を委託することが多く、申請書を受け付けした後に、調査の委託等について申請者へ連絡することがあります。
電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、下記リンクより電子申請することもできます。
※マイナンバーカードのほか、パソコン・ICカードリーダライタ、マイナポータルアプリ対応のスマートフォン等が必要です。
※更新申請については、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに認定調査を委託することが多く、申請受付後に、調査の委託等について申請者へ連絡することがあります。
医師の意見書について
- 介護認定に際しては、医師の意見書が必要になります。
- 介護を必要とする原因疾患などについて意見を書くことができる医師を主治医(かかりつけ医)としてください。
- また、介護認定に際して主治医意見書を書いてもらえるかどうか、被保険者ご本人やご家族などから医療機関へ電話等で確認してください。
- 医療機関への正式な意見書作成依頼は、介護保険課から行いますが、最後の受診日から長期間経過しているなどの理由で意見書を書くことができないと医療機関から断られる事例もあります。意見書が届かないと資料がそろわず認定することができません。あらかじめご本人やご家族の方から医療機関への確認をお願いします。
代行申請について
代行申請できる者
申請については、被保険者ご本人またはご家族・成年後見人などのほか、地域包括支援センター、厚生労働省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
現況状況(兼)認定調査連絡票
介護保険課では、要介護(要支援)認定に係る申請(新規申請や区分変更申請)を受け付けると、対象者の状況把握や認定調査の日程調整などのため、申請者の方などへ聞き取りを行っています。
その際に使用している聞き取りシート(「現況状況(兼)認定調査連絡票」)を参考までに掲載しますので、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などが新規申請や区分変更を被保険者ご本人の代わりに行う場合に、ご活用ください。
(令和5年9月から様式を変更しています。)
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
届出が必要なとき
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したとき、または居宅サービス計画(ケアプラン)の内容を変更したとき
居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書について
介護保険負担限度額認定申請書(食費・居住費(滞在費)の軽減制度)
申請が必要なとき
市民税非課税世帯(世帯が分かれている配偶者がいる場合は配偶者も市民税非課税)の方で預貯金等の資産が一定額以下の方や、生活保護受給者が、介護保険施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用するとき
介護保険居宅サービス利用者負担額減額(免除)申請書
申請が必要なとき
介護保険料第1段階(生活保護受給世帯は除く)、第2段階、特例第3段階及び第3段階に該当する市民税非課税世帯の方が居宅サービスを利用するとき
要介護(要支援)認定の申請中に被保険者がお亡くなりになった場合の取扱いについて
要介護(要支援)認定申請中に、被保険者が亡くなられた場合は、申請区分や審査判定資料の進み具合により、以下のとおり取り扱います。
- 申請日から亡くなられた日までの間に暫定ケアプランに基づく介護サービスの利用がない場合は、認定の必要がありません。(申請の取下げとなります。)
- 認定調査前に亡くなられた場合は、審査判定に必要な資料がそろわないため、認定手続きを行うことができません。(申請の却下となります。)
- 更新申請中で、以前の認定の有効期間内に亡くなられた場合は、有効開始日時点で資格喪失されているため、認定できません。(申請の却下となります。)
- 認定調査が済んでおり、かつ、申請日から亡くなられた日までの間に暫定ケアプランに基づく介護サービスの利用がある場合は、主治医意見書の提出を受けたうえで、認定手続きを継続します。(認定結果確定後、認定結果を通知します。)
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 認定担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9125
ファクス:048-965-3289